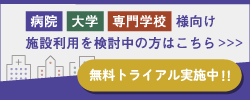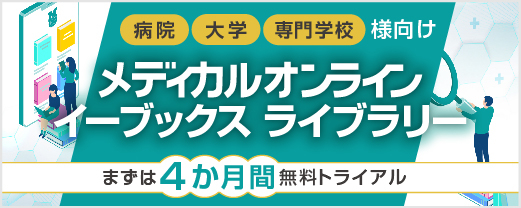| 書籍名 |
精神科医もできる! 拒食症身体治療マニュアル |
| 出版社 |
金芳堂
|
| 発行日 |
2014-07-01 |
| 著者 |
|
| ISBN |
9784765316118 |
| ページ数 |
59 |
| 版刷巻号 |
第1版第1刷 |
| 分野 |
|
| 閲覧制限 |
未契約 |
このマニュアルで精神科単科病院での拒食症(しかも重症)の治療が可能に!神経性無食欲症(拒食症)はあらゆる精神疾患の中で最も死亡率が高く、その死因には低栄養、あるいはそれに由来する身体合併症が関与していることが多い。また、不用意に栄養療法を行うと、リフィーデング症候群という致死的な合併症を生じることが知られている。そのため、精神科医は拒食症患者の入院治療を敬遠しがちであり、現在は内科や小児科で身体治療を受けた後に精神科へ転科することが一般的である。しかし、従来の方法ではANの診療が可能な医療機関は自ずと精神科病棟を有する総合病院に限定されてしまう。近年、拒食症患者が急増している一方で、総合病院の精神科病床数は減少傾向にあり、総合病院を中心とした拒食症の医療体制はいずれ立ち行かなくなることは明白である。現状を打開するためには精神科医も拒食症の身体的な病態生理を理解し、積極的に身体治療に携わるべきと考えた。そこで、浜松医科大学精神科では既存のガイドラインを参考に精神科単科病院においても利用可能な身体管理マニュアルを考案した。それは、栄養療法開始後の日数に応じて、行うべき検査を明示し、当日のバイタルサイン、諸検査結果などから投与熱量、輸液製剤とその投与速度、内服薬の種類や投与量などを具体的に規定している。当直帯や休日など、主治医が不在であっても同じ水準の医療を提供することが可能である。マニュアル導入後、その成果は驚くべきもので、まずリフィーデング症候群の発生が皆無になり、検査漏れがなくなり、入院期間が短縮され、治療方針が統一されたため、患者からの苦情がなくなり、安全かつ効率的な診療が可能となった。
目次
- 表紙
- 本書を利用される皆様へのご挨拶
- はじめに
- 本書の特徴
- 目次
- 1章 治療を始める前に
- 2章 治療マニュアル
- 注意事項
- 入院当日 ( Day 0 )
- 第1期 ( Day 1〜4 )
- 第2期 ( Day 5〜10 )
- 第3期 ( Day 11〜28 )
- 第4期 ( Day 29〜 )
- 3章 緊急時の対応
- 1. バイタルサインの異常
- 2. 低血糖
- 3. 高血糖
- 4章 治療薬と各種オーダー
- 医薬品
- 約束処方
- サプリメント・栄養補助食品
- セットオーダー
- 文献
- 奥付
参考文献
P.54 掲載の参考文献
-
2) 依藤亨 : III. 必ず遭遇する "内分泌疾患を疑わせる訴え" : 絶対に確認すべきファーストライン低血糖. 小児科診療 73:409-415, 2012
-
4) 宮田剛 : ≪輸液処方のキホン≫基本的栄養輸液処方の考え方. 内科 109 : 216-222, 2012
-
5) 中屋豊ら : リフィーディング症候群. 四国医誌 63:23-28, 2012
-
6) National Institute for Health and Clinical Excellence : Nutrition support in adults. Clinical Guideline CG32, 2006
-
7) 大村健二 : 低栄養・高カロリー輸液患者に多い電解質代謝異常. Medicina 47:1039-1041, 2010
-
8) 大村健二 : ≪栄養輸液のコントラバシー・ピットフォール≫ 栄養輸液におけるピットフォール. 内科 109:273-277, 2012
-
9) Philip SM and Arnold EA : Eating Disorders : A Guide to Medical Care and Complications 2nd edition, The Johns Hopkins University Press, 2010
-
10) 「摂食障害治療ガイドライン」作成委員会 (編) : 摂食障害治療ガイドライン. pp91-93, 医学書院, 2012
-
11) 鈴木 (堀田) 眞理 : 摂食障害の身体的治療. 医学のあゆみ 241:690-695, 2012
-
12) 浦野綾子 : 神経性食欲不振症患者におけるrefeeding症候群. 臨床栄養 119:37-42, 2011