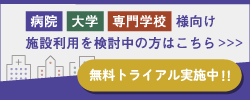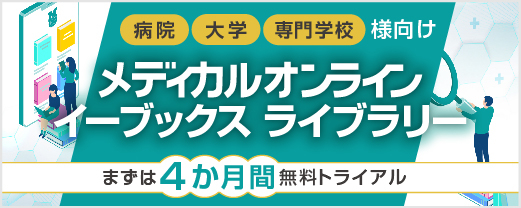| 書籍名 |
重度障害者の職業リハビリテーション入門 ―誰もが働ける社会をめざして― |
| 出版社 |
荘道社
|
| 発行日 |
2010-12-08 |
| 著者 |
|
| ISBN |
9784915878824 |
| ページ数 |
170 |
| 版刷巻号 |
第1版第1刷 |
| 分野 |
|
| 閲覧制限 |
未契約 |
障害は人生のあらゆる時期に起こり得る。そのためすべての障害者に,それぞれの受傷時期に応じて,医療や教育や労働など必要とされる多くの分野の,一貫したしかも切れ目のないリハビリテーションサービスを受ける機会が保証されるべきである.(「まえがき」より)
目次
- 表紙
- 執筆者一覧
- まえがき
- もくじ
- 第1章 職業リハビリテーションの理念
- 1. 障害者になるということ
- 2. ゆれる障害者の生活
- 3. リハビリテーションという方法
- 4. 職業リハビリテーションという方法
- 第2章 「制度の歴史」と「今日の課題」
- 1. 職業リハビリテーションの発展準備期 (1950年代〜1970年代前半) ― 身体障害者中心の雇用施策
- 2. 国レベルの総合リハビリテーション期 (1970年代後半〜1980年代) ― 福祉と労働の連携
- 3. 地域に根ざした総合リハビリテーション期 (1990年代以降) ― 残された重度障害者への対応
- 4. 今日の課題
- 第3章 「働く」を支援する現行サービス体系 ― 「働きたい」を育てるサービスの拡充をめざして
- 1. 福祉サービスの不十分さ
- 2. 労働分野におけるサービスの不十分さ
- 3. 福祉・労働の連携
- 4. 今後のあり方 ― 路線案内人システム
- 第4章 障害者とは ― 医学的・心理学的特徴
- 1. 身体障害者
- 2. 知的障害者
- 3. 精神障害者
- 4. ほかの障害
- 5. 障害者数
- 第5章 一般的な職業訓練
- 1. OJT (職場内訓練) とOFF-JT (職場外訓練)
- 2. 段階的訓練方式
- 第6章 障害者職業訓練の新しいアプローチ ― 実践の共同体
- 1. 徒弟制度は人材育成の基本
- 2. 実践の共同体の実際例 ― 集団クリーニング訓練
- 3. 実践の共同体の概要 ― 用語の整理
- 4. 実践の共同体から得たこと ― これからの職業訓練に向けて
- 第7章 人間関係 (ふれあい) に基づく支援の理論と実際
- 1. ピグマリオン型 ― 期待
- 2. 実践の共同体型
- 3. パターナリズム型
- 4. 一般的な動機づけ方法による支援
- 5. 「個人の能力」対「人間関係に基づく支援」
- 第8章 利用者の自覚の促進
- 1. 生活の自覚
- 2. 労働の自覚
- 3. 気になる行動の自覚
- 第9章 職業指導員の心構え
- 第10章 職業リハビリテーションのパイオニア
- 1. 「ビズィビー」の頃
- 2. 聴覚障害者への職業訓練を行う
- 3. 実践の共同体としての集団クリーニング訓練の確立
- 4. 思い出すことなど ― 育て直し
- 引用文献・参考文献
- 奥付
参考文献
引用文献・参考文献
P.158 掲載の参考文献
-
1) 田中萬年: わが国の職業訓練カリキュラム-課題と方法. 燭台社, 1986
-
2) 佐藤宏: 能力開発. 松為信雄, 菊池恵美子(編): 職業リハビリテーション学, 改訂第2版, 協同医書出版社, 2006
-
3) 道脇正夫: 障害者の職業能力開発 「理論編」. 雇用問題研究会, 1997
-
4) 春見静子: 各種保護雇用の取組み. 「EU諸国における障害者差別禁止法制の展開と障害者雇用施策の動向」, 調査研究報告書 No.81: 障害者職業総合センター, 2007
-
5) 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(編): 就業支援ハンドブック. 独立行政法人高齢・障害者支援機構, p.27, 2009
-
6) 笠原嘉: 精神病. p.78, 岩波書店, 1998
-
7) 宗像元介: 職人と現代産業. 技術と人間, 1996
-
8) 厚生労働省職業能力開発局(監): 職業訓練における指導の理論と実際. 9訂版, 職業訓練教材研究会, 2007
-
9) 丹羽真一, 福田正人(監訳): 統合失調症の認知機能ハンドブック. p.72, 南江堂, 2004
-
10) 田中萬年: 職業訓練原理. pp.1-5, 職業訓練教材研究会, 2006
-
11) 市川伸一: 学習と教育の心理学. 岩波書店, 1995
-
12) Lave & Wenger(著), 佐伯 胖(訳): 状況に埋め込まれた学習. 産業図書, 2003
-
1) 平川政利: 職業リハビリテーション施策の変遷と課題. 障害者職業総合センター, 1996
-
2) 松井亮輔: 障害者権利条約制定とその国内的意義. 「ノーマライゼーション 障害者の福祉」第21巻, 日本障害者リハビリテーション協会, 2001
-
3) 道脇正夫: 身体障害者職業訓練の歩み-職リハ研修教材研修テキスト(3). 国立職業リハビリテーションセンター, 1984
-
4) 三ツ木任一: 職リハのこれまで. 職業リハビリテーション学会誌 16: 日本職業リハビリテーション学会, 2003
-
5) 森口弘美, 久保真人: 障害のある人の就労の現状と障害者自立支援法の問題点. 同志社政策研究 創刊号: 同志社大学政策学会, 2007
-
6) 七瀬時雄: 障害者雇用政策の理論と解説. 労働行政研究所, 1995
-
7) 労働省(編): 最新労働用語辞典. 日刊労働通信社, 1993
-
8) 職リハ用語検討研究委員会(編): 職リハ用語集. 第2版, 日本職業リハビリテーション学会, 2002
-
9) 田中萬年: 「職業能力開発促進法」の改正と公共職業訓練の再編成. 技術教育研究第41号. 1993
-
10) 田中萬年, 道脇正夫, 平川政利: 職業リハビリテーションの変遷と課題. 職リハ調査研究資料第14号. 国立職業リハビリテーションセンター, 1996
-
11) 田中萬年, 大木栄一(編): 働く人の「学習」論. 第2版, 学文社, 2007
-
12) 安井秀作: 職業リハビリテーション. 中央法規出版, 1989
-
13) 平川政利」国立職業リハビリテーションセンターにおける職業訓練の実践. 「精神障害者の職業訓練指導方法に関する研究」. 障害者職業総合センター調査研究研究報告書 No.70. 障害者職業総合センター, 2006
-
14) 厚生労働省職業能力開発局能力開発課: 新たな障害者職業能力開発の展開. 職業能力開発ジャーナル 46: 14-18, 2004
-
15) 道脇正夫: 障害者の職業能力開発. 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(編): 障害者雇用ガイドブック. 雇用問題研究会, 2007
-
16) 職業リハビリテーション部: 高次脳機能障害者(編): 職業的重度障害者に対する職業訓練・指導技法等実技報告(1). 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構, 2004
-
17) 上田典之: 問題予測とよりよい行動への支援-高次脳機能障害を持つ方への職業訓練実施例. 技能と技術 3: 2004
-
18) 海外職業訓練協会(OVTA): 米国-職業能力開発の政策と実施状況, 2007
-
19) 茂木健一郎: 脳を活かす勉強法. PHP研究所, 2008
-
20) 南雲直二: エッセンシャル・リハビリテーション心理学. pp.77-79, 荘道社, 2006
-
21) 田中萬年: 生きること・働くこと・学ぶこと. p.21, 技術と人間, 2002
-
22) 佐藤忠夫: 学習権の倫理. 平凡社, 1973
-
23) 平川政利, 南雲直二, 若林耕司, 近藤和弘: 実践の共同体による指導の原理と課題. 第15回職業リハビリテーション研究会発表. 高齢・障害者雇用支援機構, 2007
-
24) 若林耕司, 南雲直二, 平川政利, 吉田喜三: 実践の共同体と動機付けとの関連(1). 第15回職業リハビリテーション研究会発表. 高齢・障害者雇用支援機構, 2007
-
25) 若林耕司, 南雲直二, 平川政利, 吉田喜三: 高次脳機能障害者のクリーニング訓練の特徴. 国立リハビリテーションセンター研究紀要第22号. 国立身体障害者リハビリテーションセンター, 2002
-
26) 若林耕司, 他: 高次脳機能障害者のクリーニング訓練の特徴. 国立リハビリテーションセンター研究紀要第23号. 29-33, 国立身体障害者リハビリテーションセンター, 2003
-
27) 若林耕司, 南雲直二, 平川政利, 吉田喜三: 高次脳機能障害者の集団クリーニング訓練. 国立リハビリテーションセンター研究紀要第27号. 国立身体障害者リハビリテーションセンター, 2007