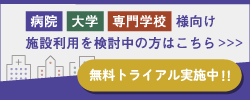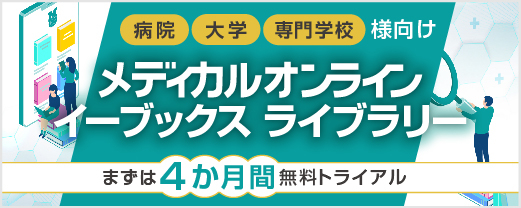書籍詳細

| 書籍名 | 図解 患者サービス読本 |
|---|---|
| 出版社 | 日本プランニングセンター |
| 発行日 | 1991-06-18 |
| 著者 |
|
| ISBN | 4931197264 |
| ページ数 | 333 |
| 版刷巻号 | 第1刷 |
| 分野 | |
| 閲覧制限 | 未契約 |
目次
- 表紙
- 推せんのことば P.5閲覧
- 執筆者一覧P.7閲覧
- 内容目次P.8閲覧
- 第1章 一般病院のインフォームド・コンセント P.19閲覧
- 第2章 インフォームドコンセント (クリニックの場合)P.33閲覧
- 第3章 ナースの応接と態度 P.65閲覧
- 第4章 訪問看護・電話医療相談・退院時指導・在宅医療 P.73閲覧
- 第5章 病院薬局における患者サービスの実際 P.87閲覧
- 第6章 患者と衣服P.111閲覧
- 第7章 患者の立場からの給食P.147閲覧
- 第8章 利用者の視点に立った病院建築P.201閲覧
- 第9章 患者の立場から要求するインテリアP.225閲覧
- 第10章 患者の立場に立った住宅の作り方P.251閲覧
- 第11章 多角経営 P.291閲覧
- 第12章 医療関連ビジネスの実態と将来P.309閲覧
- 第13章 院内患者投書箱活用による患者サービスの向上に関する一考察
- 奥付